秋が深まり、過ごしやすい気候となる一方で、原因のわからない鼻水や咳、目のかゆみといった不調に悩まされる方が少なくありません。季節の変わり目の風邪や秋バテとして見過ごされがちですが、その症状の背景には秋季花粉症が潜んでいる可能性があります。花粉症といえば春のスギやヒノキが有名ですが、秋にも特有のアレルギーを引き起こすキク科の植物が代表的で、道端や河川敷、空き地などに多く自生し、8月から10月にかけて花粉が飛散します。
1. 秋季花粉症の主な原因アレルゲン
春の花粉症がスギやヒノキといった「樹木」の花粉を原因とするのに対し、秋季花粉症の主な原因(アレルゲン)は、「草本植物」の花粉です。特に、以下の二つが代表的なアレルゲンとして知られています。
- ブタクサ 全国の道端や河川敷、空き地などに広く自生するキク科の植物です。非常に繁殖力が強く、8月から10月にかけて大量の花粉を飛散させます。その花粉は秋季花粉症における最も主要な原因の一つです。
- ヨモギ ブタクサと同じくキク科の植物で、日本各地の野山や道端でごく普通に見られます。飛散のピークは8月下旬から10月頃で、ブタクサとほぼ同時期に症状を引き起こします。
これらの草本植物の花粉は、樹木の花粉に比べて粒子が小さく、飛散距離が数十メートル程度と短いのが特徴です。そのため、スギ花粉のように広範囲に影響を及ぼすことは少ないものの、生活圏内に群生地があると、局所的に高濃度の花粉に曝露されることになります。散歩道や公園、通勤路の植え込みなどが、意図せずアレルゲンとの接触点となっているケースも珍しくありません。
2. 症状の特徴と鑑別すべき疾患
秋季花粉症の主な症状は、春の花粉症と同様に、水様性の鼻水や鼻漏、発作的に繰り返すくしゃみ、鼻づまりや鼻閉、そして眼のかゆみや充血です。
ただし花粉の粒子が比較的小さいため気道に入り込みやすく、喉の違和感や咳を伴うことも少なくありません。喘息の持病がある方は、症状が悪化する可能性もあり注意が必要です。
この時期に流行する風邪(ウイルス性の感冒)と区別することは重要です。花粉症では、通常38度を超えるような高熱は稀で、症状は花粉が飛散する期間中(数週間〜数ヶ月)持続します。一方、風邪は発熱を伴うことが多く、鼻水も次第に粘り気のある性状に変化し、通常は1週間程度で軽快します。症状が長引く場合は、花粉症を疑うべきでしょう。
最近のトピックとしては、口腔アレルギー症候群(OAS)の話をニュースやコラムでもよく目にします。これは花粉のアレルゲンと共通の構造を持つ特定の果物や野菜を摂取した際に、口腔内や唇にかゆみや腫れが生じるものです。特にブタクサ花粉症の患者さんではメロンやスイカ、キュウリなどのウリ科の食物で、またヨモギ花粉症の場合にはリンゴやセロリなどの食物で、交差反応により症状が誘発されることがあります。
3. 日常生活における予防と対策
症状の発現を抑制し、悪化を防ぐためには、アレルゲンである花粉との接触を極力避けるセルフケアが基本となります。
(いずれも医学的に症状緩和の効果が実証されているものではなく、あくまで物理的な花粉量を減らすための行動提案です)
- 外出時の注意
- マスクや眼鏡、帽子を着用し、花粉の吸入や付着を防ぐことは症状の悪化予防に効果があるかもしれません。
- ウールなどのけば立った素材を避け、表面が滑らかな化学繊維の衣類を選ぶことで花粉を自宅内や部屋の中に持ち込みにくくなります。
- ブタクサやヨモギの群生地には近づかない。
- 帰宅時の対策
- 家に入る前に、衣服や髪に付着した花粉を丁寧に払い落とす。
- 帰宅後は速やかに洗顔、うがい、手洗いを行い、可能であればシャワーを浴びる。
- 室内環境の整備
- 空気清浄機を適切に利用する。
- こまめに室内を清掃する。特に床の花粉は舞い上がりやすいため、濡れた布での拭き掃除が効果的である。
4. 医療機関における診断と治療
- 診断 問診に加え、血液検査(特異的IgE抗体検査)などを行い、原因アレルゲンを特定します。正確な診断が、適切な治療への第一歩となります。
- 薬物療法 症状を緩和させるための対症療法です。第二世代抗ヒスタミン薬の内服を基本に、鼻症状が強い場合は鼻噴霧用ステロイド薬、眼症状には抗アレルギー点眼薬などを組み合わせて使用します。症状が出始める少し前から服用を開始する初期療法は、シーズン中の症状を軽減する上で有効とされています。
- アレルゲン免疫療法 アレルギーの原因物質を少量ずつ投与し、体をアレルゲンに慣らすことで、アレルギー反応そのものを抑制、あるいは根治を目指す治療法です。日本ではまだスギ花粉とダニアレルギーの薬のみ承認されている状況ですが、海外ではブタクサ花粉症に対しては舌下免疫療法が保険適用となっている国も多く、治療には3年以上の期間を要しますが、長期的な症状改善や薬剤の使用量減少が期待できます。
執筆者
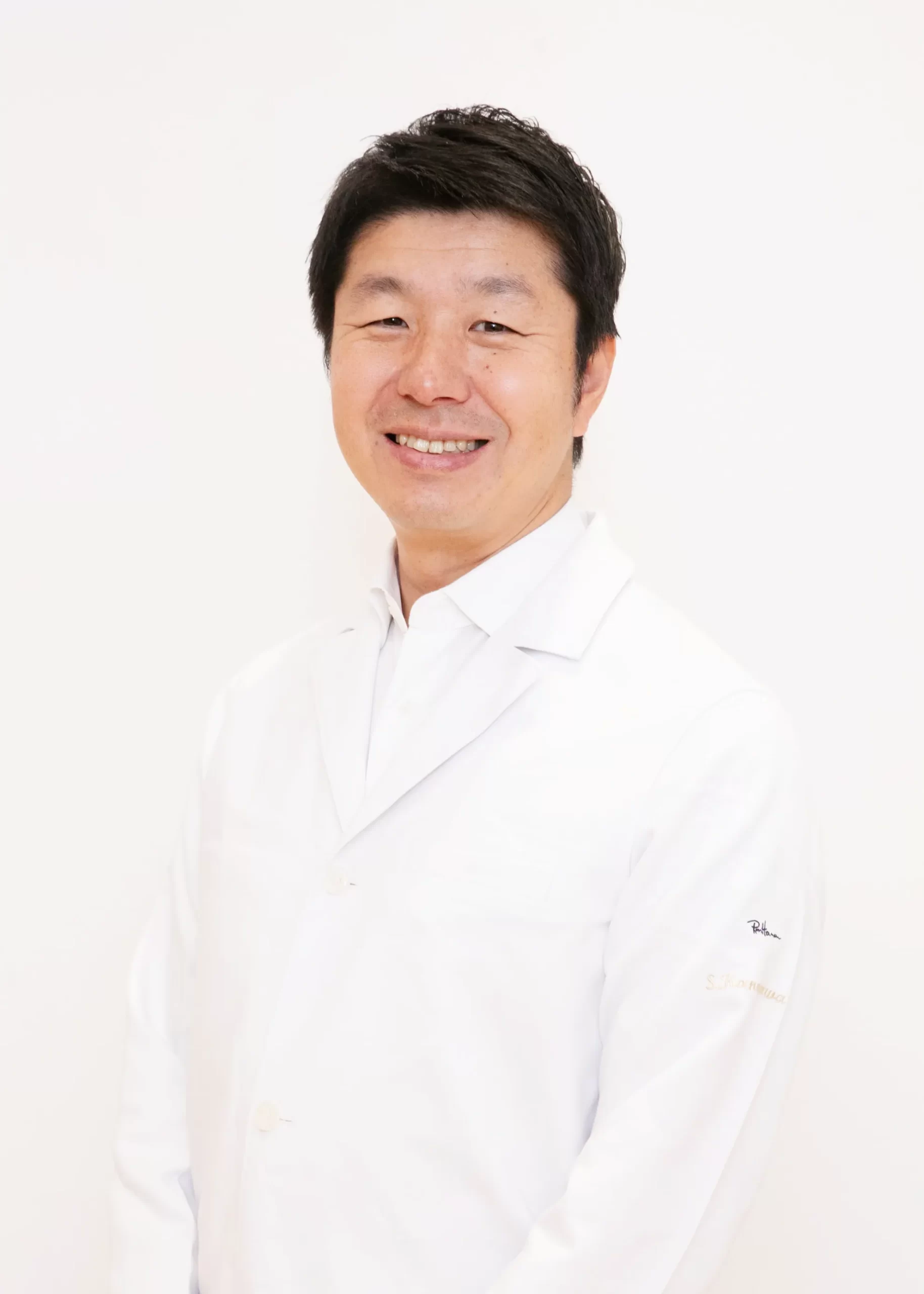
医療法人社団クリノヴェイション理事長
内藤 祥
経歴
北里大学医学部卒
沖縄県立中部病院で救急医療、総合診療をトレーニング
沖縄県立西表西部診療所で離島医療を実践
専門は総合診療
資格
日本プライマリ・ケア連合会認定 家庭医療専門医・指導医
日本内科学会 認定医
日本医師会 認定産業医
日本旅行医学会 認定医
日本渡航医学会 専門医療職






